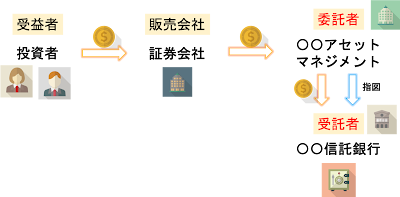今日は「投資信託及び投資法人に関する業務」の第2回です。投資信託の分類を紹介します。
試験のキーワードになりそうな用語を赤色で示します。その他の色は、理解を助けるためにつけます。出題分野名は「投資信託及び投資法人に関する業務」が正式名称ですが、記事のタイトルに書くには長すぎるので「投資信託等に関する業務」と表記します。
* * *
(よろしければ、こちらからチャンネル登録お願いします)
* * *
上の動画のポイントをまとめます。
1 投資家による分類
投資信託は、販売対象によって公募と私募に分類されます。50名以上の投資者に販売するとき、公募投資信託といいます。私たち個人投資家が購入する投資信託は、このタイプの投資信託です。50名未満の投資者に販売するとき、私募投資信託といいます。また、適格機関投資家と特定機関投資家のみに販売するときもこの私募投資信託といいます。次のリンク先資料(金融庁)をみると、適格機関投資家として、証券会社、銀行、信金、短資会社、農協などが掲げられています。特定機関投資家として、国、日本銀行、特殊法人、預金保険機構などが掲げられています。
https://www.fsa.go.jp/common/law/tekikaku/index.html
https://www.fsa.go.jp/common/law/tokutei/index.html
多くの投資者に販売することを公募、少数の投資者またはプロの投資者に販売することを私募と覚えると整理しやすいかと思います。
2 組み入れ資産による分類
投資信託は、組み入れる資産によって公社債投資信託と株式投資信託に分類されます。公社債投資信託には、株式を組み入れることができません。株式投資信託には、株式を組み入れることができます。MRFやMMFは公社債投資信託の例です。どちらも国債や格付けの高い社債、コマーシャルペーパーなどに投資します。1口1円で毎日決算することも共通しています。証券口座を開いている人にとって、銀行預金のような役割を果たしています。
MRFとMMFの違いは、MRFが解約手数料が無料なのに対して、MMFが30日以内に解約するとき手数料を払う点です。MRFは普通預金、MMFは定期預金に商品性が似ています。
下のリンク先から投資信託協会のデータをみると、2017年5月以降、MMFの残高は0です。これは、2016年2月にマイナス金利が導入され、運用で資産を殖やせる状況から、運用すると資産が減る状況に変わったことを反映しています。
https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/
私たち個人投資家が目にするほとんどの投資信託は、株式投資信託です。たとえば、株価指数に連動するETF(上場投資信託)は、株式投資信託です。
注意していただきたいのは、株式投資信託はあくまで株式に投資できる投資信託であることです。ある時点で、株式に投資していなくても、株式に投資する可能性がある投資信託は株式投資信託に分類されます。
3 解約・換金方法による分類
投資信託は、解約できるかどうかによってオープン・エンド型とクローズド・エンド型に分かれます。オープン・エンド型は解約できます。クローズド・エンド型は解約できません。オープン・エンド型は、投資を終えたい投資者は解約を申し出ます。解約するとき、投資信託の純資産額(時価総額のようなもの)にもとづいて、返金される金額が決まります。解約が生じると、投資信託の資金量は減ります。したがって、オープン・エンド型の投資信託は資金量が不安定です。
クローズド・エンド型は、解約できませんので資金量が安定しています。これは投資信託を運用する側の利点です。しかし、投資者は解約ができないと困ります。投資者は市場で他の投資者に売ることで投資信託を現金化します。したがって、クローズド・エンド型の投資信託は証券市場に上場しています。
不動産投資信託(J-REIT)は、クローズド・エンド型投資信託の例です。投資法人を設立し、投資者から集めた資金の70%以上を不動産等で運用します。不動産投資信託が発行する投資口は、東京証券取引所で自由に譲渡できます。詳しくは、次のリンク先資料を見てください。
https://www.toushin.or.jp/reit/about/scheme/
4 ETF
上場投資信託(ETF)とは、東京証券取引所で自由に売買できる投資信託です。普通の株(トヨタや任天堂の株など)とおなじように、指値注文、成行注文を出して売買できます。信用取引もできます。日経平均株価やTOPIXのインデックスに連動するETFに人気があります。私たち一般投資家にとって、市場で売買するETFはクローズド・エンド型です。これに対して、大口投資家は、現物株式を拠出することで受益権を取得することができます。少し複雑なしくみになっています。詳しくは、次のリンク先資料を見てください。
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/etf/scheme/
投資信託の分野は、他の分野に比べて覚えるのが大変です。無理せず少しずつ慣れていきましょう。
* * *
このブログでは、各科目の幹となる用語や計算問題を紹介します。細かい用語や最新の法令・規則については、テキストや問題集で確認をお願いします。